遺産分割協議(書)とは?
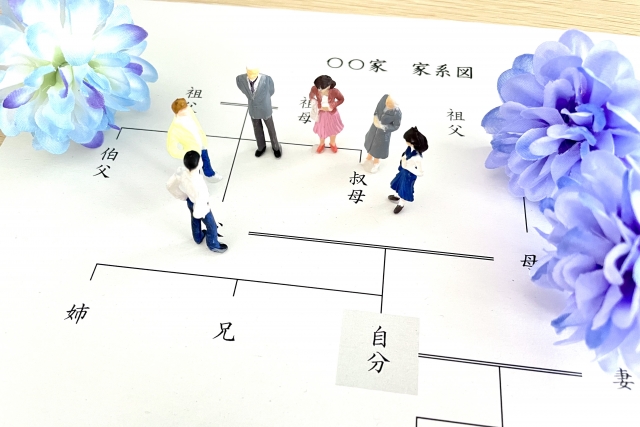
人が亡くなると相続が発生します。その場合、被相続人(亡くなった方)が遺言を残していた場合は、その遺言の内容に従って相続手続きを行いますが、遺言が存在しない場合には、相続人全員で相続財産の分け方話し合って決めます。
この話し合いのことを「遺産分割協議」と言い、その協議内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議が調わなかった場合、相続人は、分割を家庭裁判所に求めることができます。
遺産分割をする時期についてですが、民法は「遺言において遺産分割の禁止がなされていない限り、相続人はいつでも分割を求めることができる」としています。
ですので、何らかの必要性が生じた段階で、はじめて遺産分割をなすことも可能です。
(それまでの間に、個々の財産について取得時効が完成したり、持分権が処分されたことによって遺産分割の対象から外れることはあります)
遺産分割協議の当事者
遺産分割協議の当事者は、共同相続人のほか、包括受遺者、相続分の譲受人、(遺言執行者)です。
当事者の一部を欠く分割協議は無効です。
相続人となるべき者が行方不明の場合には、不在者の財産管理人を選任し、遺産分割協議を行います。
未成年者の場合は、親権者または特別代理人が参加し、認知症となった者がいれば成年後見人などが本人のかわりに遺産分割協議に参加します。
遺産分割の方法
遺産分割の方法は以下の通りです。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 現物分割 | 不動産は妻、預金は長男、株式は次男、というように遺産を現物のまま分割する方法。遺産を共同相続人に現実に分けて分割するものであり、例えば遺産が土地であれば、分筆するなどして分割する |
| 代償分割 | 現物を特定の者が取得し、取得者は他の相続人にその具体的相続分に応じた金銭を支払う方法。現物を取得する相続人にその支払い能力があることが必要です。また、分割協議で代償金の支払いを約束した相続人が、約束を破って支払いをしないこともあり得るので、代償金を受ける相続人はリスクがあります。 |
| 換価分割 | 遺産の中の個々の財産を売却し、その代金を配分する方法。 |
| 共有分割 | 相続財産を遺産分割協議や法定相続分に応じて共有するという方法。「現物」「換価」「代償」分割が困難なときに選択される。 |
遺産分割協議書の作成
成立した遺産分割協議書によって具体的な相続手続き(預貯金の払い出し等)を行う場合には、遺産分割協議書の作成が必要になります。
遺産分割協議書には協議の内容を記載し、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。また、遺産分割協議書が2枚以上になる場合はつながりを証するために用紙と用紙の間の契印をわすれないようにしましょう。
遺産分割協議書作成の要点は次のとおりです
- 「誰が」「どの財産を」「どれだけ」取得するのかを明記する
- 現在判明していない相続財産が今後発見された場合、だれが取得するのか記載する
(記載がない場合は、遺産分割協議成立後に発見された相続財産について、再度遺産分割協議を行わなければならなくなります。)
- 住所は印鑑登録証明書のとおりに記載する
- 各相続人が1通ずつ所持できるように、相続人の人数と同じ通数の遺産分割協議書を用意する。
