

遺言書の検認とは?
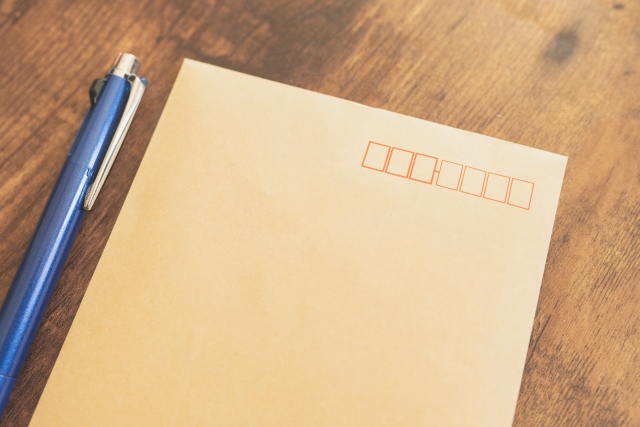
公正証書遺言ならびに法務局に保管された自筆証書遺言を除いて、遺言については、家庭裁判所で検認手続きを経なければならないと民法に規定されています。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状や状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
検認は上記のように証拠を保全するための手続きであるため、遺言が有効なものであるかどうかとか、遺言が遺言者の真意に基づくものであるかどうか等の実質的な判断を行う者ではありません。
つまり、検認を経た後で、その遺言書が、遺言者によって作られた真正のものではないといったことを争う事が可能です。
例えば:遺言の付言(法的効力はないが気持ちなどを記すことができる)特定の相続人に対して恨みつらみを残したりすると、その相続人から「その遺言は偽物だ!」ということで争う事は可能であるということです。
検認手続きの流れ
- 遺言を保管していた人または遺言書を見つけた相続人が申立人となり、遺言書の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申立てを行う
- 家庭裁判所から申立人およびすべての相続人に対して検認の期日の通知が届けられる
- 検認の期日に、申立人および相続人立会のもとで、家庭裁判所で遺言書が開封される
- 家庭裁判所は、遺言の形状(遺言書がどのような用紙に、何枚書かれていたか、封はされていたかなど)、遺言書の加除訂正の状態、遺言書に書かれた日付、署名・印など遺言の内容がどうなっていたかについて確認し、この結果を検認調書のまとめて検認が終了する。
検認終了後、申立人または相続人等は家庭裁判所で「検認済証明書」の発行を申請すると、遺言書に検認済証明書を添付したものが交付されます。公正証書遺言以外の遺言によって相続の手続きを行うには、この検認済証明書が添付された遺言書が必要になります。
検認の手続きが完了するには、家庭裁判所に検認の申立てをしてから1カ月程度要します。