
大阪相続・遺言アシストステーション

遺言の効力
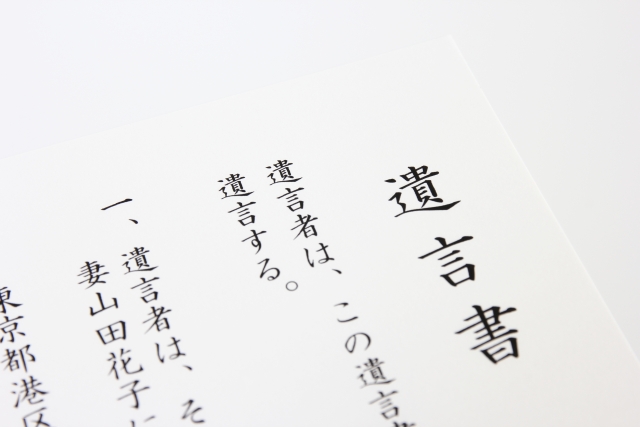
民法上、遺言は原則「法定相続分」に優先します。
つまり人が亡くなった時に、「遺言」があれば、そちらが優先され「遺言」の通りに財産が引き継がれます。
遺言の効力が発生するのは遺言者の死亡の時点ですが、この「遺言」が有効なのか?無効なのか?というのはどのようにしてきまるのでしょうか?
遺言というのは、その方式が非常に厳格に規定されている要式行為です。
前述したように、遺言の効力が発生するのが、遺言者の死亡の時点なのですが、その時点では、もはや遺言者自身の意思を確認できないなので、方式が厳格に規定されているわけです。
また、要式以外にも遺言を作成する上でいくつかの約束事があります。それは
- 遺言能力
遺言は15歳以上ですることができる
意思能力が必要(判断の基準として遺言時に意思能力があったことが必要) - 共同遺言の禁止
遺言は2人以上の者が同一の証書ですることはできない - 遺言の撤回
遺言はいつでも撤回することができる
です。
これら約束事が守られていなければなりません。
すでに触れましたが、遺言は厳格な要式行為です。これは、遺言の効力が発生した時点では、もはや遺言者自身に意思を確認することができないことから、可能な限り疑義が生じないようにすることを目的としているからです。
また、遺言者が、もはや自らの意思を表明することができない以上、その真意をできるだけ尊重してあげたいということもあるのでしょう。
民法は一般的な遺言の方式として、3つのものを用意している。
- 自筆証書遺言
・遺言の内容となる全文、日付、氏名を全て自筆する。
・押印する
・財産目録は自筆でなくてもよいが、目録の各ページに署名、押印しなければならない - 公正証書遺言
・証人二人の立会
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する
・公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させる
・遺言者および証人が筆記の正確なことを証人した後、各自これに署名し、印を押す
・公証人がその証書を上記に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押す - 秘密証書遺言
・遺言者による証書への署名押印
・遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印する
・遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名および住所を申述する
・公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押す
遺言の有効性の確認
作成された遺言の有効性に疑義がある場合、相続人や第三者によって遺言の効力が争われる場合があります。
遺言の有効性に争いが生じた場合には、遺言の執行に先立ち、遺言無効確認請求訴訟などへの対応が必要となることがあります。
遺言が無効になるケース
前述の約束事や厳格な要式行為であることをふまえて、遺言が無効になるケースを見てみましょう。
- 遺言能力
民法では、遺言能力について「遺言者は遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と規定しています。
このため、遺言時に遺言者が認知症等により事理弁識能力を欠いていたような場合には、遺言が無効となる可能性があります。
遺言能力の判断に当たっては、医師作成の診断書や検査記録、入院記録等の医療記録が重要な資料となります。
遺言能力に関する争いが激しい場合には、遺言無効確認請求訴訟が提起され、訴訟の中で鑑定などが行われることもあります。 - 自書性(自筆証書遺言)
自筆証書遺言の自書性が欠ける場合、遺言は無効となります。
よくあるケースとしては、遺言が偽造されたものかどうか(他人が勝手に作成したものであるかどうか)というものが挙げられます。自書性に争いがある場合には、筆跡鑑定などを行う事もあるでしょう。 - 方式要件を満たしていない
自筆証書遺言の自書性以外にも、遺言が民法の定める方式に従っていないことを理由として、無効とされる場合があります。
ただし裁判例においては、軽微な方式違いでは遺言が無効と判断されなかったケースも多くあります。
例えば、遺言作成の日付に誤記があるものの、真実の作成日が遺言書の記載から明らかであるような場合には、遺言は無効とならないとした裁判例(最判昭52・11・21裁判集民122・239)。や
押印についても、遺言書本文に押印がなかった場合でも、遺言書本文の入っていた封筒の封印に押印があれば、押印の要件を満たすといった裁判例もあります。(最判平6・6・24裁判集民172・733)。 - 公序良俗違反など
遺言は公序良俗違反により無効になる可能性があります。
裁判例では、不貞行為や内縁の妻に対する包括遺贈を控除良俗違反としたものなどがあります。
そのほか、錯誤や詐欺、脅迫なども問題となり得ます。ただし、通常遺言の有効性が争われるのは遺言者の死後になるため、これらを立証することは大変困難でしょう。
遺言が無効となった場合
遺言無効確認請求訴訟により遺言の無効が確定した場合には、遺言が無かった場合と同様、遺産分割協議を行う必要があります。